2021-12-07
モグラたたき的問題
一難去ってまた一難。
次から次に問題が起こる。
一つに対処しても、またすぐ次の問題が起きる。
問題ばかりで気が休まらない。そうしてうんざりしてしまうこと、ありませんか?
私も若い頃、次々に起こる問題に対処し続けて、疲弊してしまったことがあります。
本当に疲れますよね。
さて、このように次々問題が起こるとき、目の前の問題にばかり対処していても、解決することはできません。
古代中国の墨子という思想家はこう言っています。
「乱のよって起こる所を知って、よく之を治む」
乱がおこる根本的な理由を知ってはじめて、乱を納めることができる、という意味です。
要するに、問題がおこる根本的な原因を把握して、そこに手を打たない限り、真の問題解決にはならないということです。
問題を引き起こす原因がそのままなら、一つの問題を解決しても、またすぐ次の問題が出てきます。
まるでもぐら叩きのように次々に問題が顔を出すのです。
その状態が続けば、対処に追われて疲れるだけでなく、組織全体が活力を失っていきます。
そうならないためには、なぜその問題が起こるのか、真の原因を探りましょう。
例えば、ミスが続く場合、そのミスを誘発している原因を探ります。
仮にコミュニケーション不足からミスが起こっているのなら、なぜコミュニケーション不足に陥っているのかを探ります。
このように原因を深掘りしましょう。
すると、問題の原因が見えてきます。
表面上は色々な問題が起こっているように見えても、根っこは同じ原因だったりします。
真の原因に対処できれば、多くの問題が一度に解決しずいぶん楽になりますよ。
前後の記事
次記事
価値を高める補完財
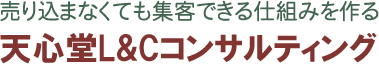
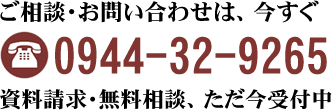
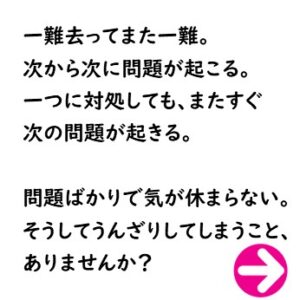
コメントを残す