2025-10-02
地域貢献と赤字の狭間で―個人宅の訪問の持続可能性
先日、一般社団法人 日本保険薬局協会が『2026年度改定における在宅業務に係る要望事項 ー薬剤師の個人宅向け在宅業務実態に関する大規模調査よりー』という資料を公開していました。
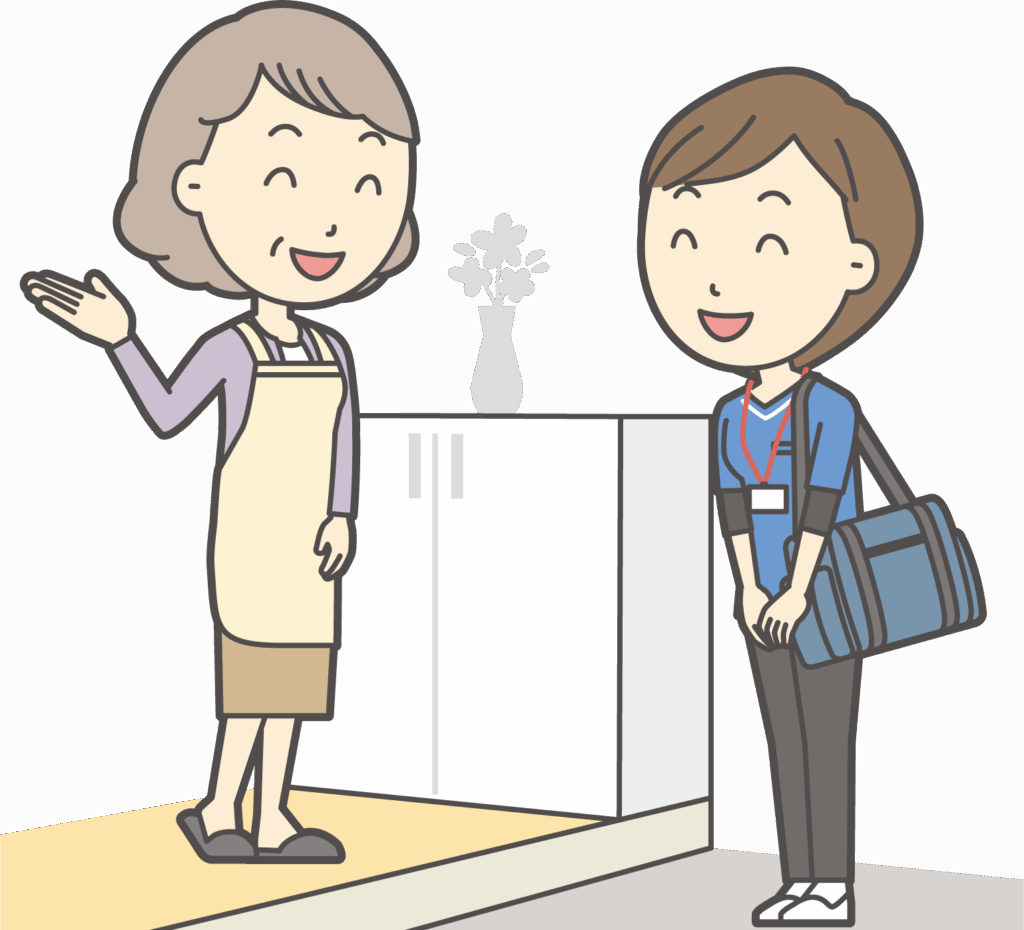
非常に興味深い内容だったうえ、薬局経営に大きく関与するお話だったので、紹介したいと思います。
一部よく分からない記載もありましたが、地域医療に貢献したいという想いを片手に、算盤をもう片手にもって薬局運営に当たらないと、結構厳しいことになるのでは?という感想です。
個人宅の在宅訪問は大赤字?
まずは同資料で気になったところをご紹介します。
特に気になった内容は「個人宅の訪問は大赤字」ってところです。
1.1訪問にかかる作業時間は98分に及んでいる。
2.訪問で最も時間がかかっているのは移動時間で25分を占めている。
3.薬局の人件費を薬剤師1人・1時間換算した給与費は4,890円
4.在宅1訪問の1時間当たりの収益は4,715円
5.人件費以外にも経費が掛かるから、個人宅の在宅は結構な赤字になる
という感じでしょうか。
正直、薬局の人件費を薬剤師1人・1時間換算した給与費は4,890円という部分は、よく分からない計算になっています。
第24回医療経済実態調査によると、薬局の年間給与費は3,662万円だそうです。
同調査をざっと眺めてみたところ、保険薬局全体の給与費は36,662千円と記載されているものは見つけました。
若干差はありますが、こんなところなのでしょう。
一方、薬局に勤務する薬剤師数は平均3.6人、薬剤師以外は2.9人だそうです。
で、人件費の3,662万円を2080時間(週40時間×52週)で割り、さらに薬剤師所属人数で割ると1時間当たり
4,890円になります。
36,620,000÷2080÷3.6=4,890
正直、
●なぜ薬剤師所属人数3.6だけで割っているのか
●薬剤師以外の2.9人はどこ行った?
●人件費には役員報酬とか調剤に直接従事しない本部社員の給与も入ってるんじゃないか
●残業代も入っているんじゃないか
とか、よく分からないところはいろいろあります。
が、在宅訪問の仕事は薬剤師さんだけで成り立っているわけではなく、事務さんや本部社員さんの力も必要なわけですから、ここはあまり深く突っ込まずに先に進みます。
さて、在宅をやるために1時間4,890円の人件費がかかっているだけではありません。
委託費や設備投資(減価償却費)、その他の経費まで掛かっているというのはその通りだと思います。
一方、在宅1訪問当たりの収益を1時間あたりに直すと、4,715円だそうです。
この計算からは調剤時間を抜いているとのこと。
外来同様の調剤部分は抜いて、訪問部分の報酬だけをコストと比べたいということなのでしょう。
で、得られる報酬4,715円<かかるコスト4,890円(+もろもろの経費が上乗せ)なので、個人宅の在宅訪問は大赤字、というわけです。
ネックは移動時間
先ほどの人件費のように、計算の仕方によっては数字が変わってきてしまうので、単純に個人宅の在宅はやらないほうが良い、なんていうつもりはありません。
が、「地域の高齢者が困っているから、ガンガン個人宅に訪問するぞ!」というのも、持続可能じゃないと思います。
私も薬局経営をしていたころは、「30年のかかりつけ」をスローガンに掲げ、OTC販売→外来→在宅までずっとかかわり続けたいと考えていました。
そのため在宅もほぼ個人宅の訪問だけでした。
ただ、算盤をはじいてみると、個人宅の在宅はやればやるほど経営的にはキツいことが多かったのも事実です。
ネックなのは「移動時間」です。
基本的にお国の仕事は移動時間に報酬は発生しません。
作業時間しかお金にならないのです。
当たり前っちゃ当たり前で、移動時間に報酬が出るなら、やたらと遠方の仕事を受けてしまえばウハウハになるからです。
これは中小企業診断士として受託する公的業務も同じで、ほとんどの場合、移動にかかるコストは全てこっちもちです。
一方、経営者側からすると、当然ながら、移動時間も給料を払わなければなりません。
つまり、移動時間が長ければ長いほど、コストが増大し収益性が悪くなるわけです。
訪問介護も厳しくなっている
実際、訪問介護などでは移動時間の長さが経営に直結していること示唆されています。
独立行政法人福祉医療機構が公表している「2022年度 訪問介護の経営状況について」という資料によれば、訪問介護を提供している営利法人の平均的な移動時間は12.9分、赤字事業所の割合は29.9%となっています。
さて、これらの事業所を同一建物減算の有無で分けたところ、明らかな差が出ます。
訪問介護の同一建物減算の要件は
①事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者にサービスを提供した場合、
②同一敷地内建物等以外の建物で、1月当たり20人以上の利用者が居住する集合住宅に居住する利用者にサービス提供した場合、
のいずれかに該当する場合、減算を行うことになっています。
効率が良いサービス提供ができる場合に減算されるイメージだと思います。
さて、同一建物減算がない事業所の場合、以下のような特徴があります。
●併設型事業所の割合:37.4%
※福祉医療機構に問い合わせたところ、「内容にかかわらず、何かしらの事業所が併設されている訪問介護事業所の割合とのこと」
●平均移動時間:16.7分
●人件費率:65.0%
●サービス活動増減差額比率(≒営業利益率):6.3%
●従業者1人当たりサービス活動収益:5,290千円
●赤字事業所割合:35.2%
一方、同一建物減算がある場合はこんな感じです。
●併設型事業所の割合:78.6%
●平均移動時間:7.3分
●人件費率:53.1%
●サービス活動増減差額比率(≒営業利益率):9.2%
●従業者1人当たりサービス活動収益:7,375千円
●赤字事業所割合:22.1%
同一建物減算ありのほうが移動時間が短く、経営指標も明らかに良いのが分かると思います。
昨今、訪問介護事業所が地域から次々に撤退しているとの報道が相次いでいます。
人手不足も大きな要因ですが、施設等を中心に効率的にサービス提供しなければ収益が上がらない構造になっているのも、経営的に厳しくなる要因だと思います。
収益が上がりにくければ人件費に回すお金がなくなるので、ますます経営は困難になります。
数年前に、訪問理美容を立ち上げたいというご相談に対応したことがあります。
実はその時も同じように、移動時間に発生する人件費を回収するのが困難なため、施設中心に営業しなければ経営が成り立たない、という結論になりました。
つまり
「住み慣れた自宅で暮らしたい」
「自宅で医療を受けたい」
という気持ちに寄り添おうとすればするほど、経営的には困難になるわけです。
にもかかわらず、先ほどの記事では「訪問介護サービスの単価が引き下げられている」と報じられています。
一方、最低賃金はこれからしばらくの間、毎年7.3%のペースで上がり続ける見込みです。
個人宅の在宅医療はますますきつくなるのでは・・・という危惧
薬局が行う在宅医療も、同じような経過をたどるのではないかと危惧しています。
つまり、人件費はどんどん上がるのに、報酬は一定か、下手したら下がるかもしれない。
ただでさえ個人宅の在宅は赤字になりやすいのに、ますます赤字幅が拡大するかもしれない。
患者さんに寄り添いたいという想いはとても大切ですが、それと同じくらい「持続可能である」ということも大切です。
地域に薬局が無くなれば、医薬品の適正使用や物流を担う機能が失われかねません。
想いを右手に、算盤を左手に
考えられる対策は、「想い」と同時に「算盤」も持つことだと思います。
個人宅の訪問で利益は出なくても、地域支援体制加算の実績要件が満たせるなら、トータルで収支はプラスになることもあるでしょう。
個人宅の訪問で赤字が出たなら、他の取り組みで黒字を出して補填するというのも一つの考え方です。
もしくは報酬だけでは赤字でも、プラスαで収益減をつくれないかを考えることもできるかもしれません。
2025年7月28日の日経新聞に『訪問介護、5分550円で「保険外」の困りごとお手伝い SOMPOケア』という記事が掲載されていました。
介護保険では、同居家族のための家事などは対象外なので介護保険内でのサービス提供はできません。
でも、別料金を取って「保険外」としてサービスを提供することはできます。
5分550円で様々なお手伝いをするサービスだそうで、2024年4月からサービスを始め、1年間の利用回数は6,000件に達したそうです。
報酬だけでは収益的に厳しくても、新しい取り組みを付加することで収益力を高められないかを検討できるのではないでしょうか。
ともあれ、医療・福祉の負担はますます重くなり、現役世代の負担感は増す一方です。
在宅医療も、短時間で効率よくこなさなければ持続できないようになりつつあります。
その傾向は今後さらに強くなるのではないかと思っています。
想いと算盤を両輪として、持続可能な薬局経営に取り組んでいただければと思っています。
薬局経営をサポートしています
天心堂L&Cコンサルティングでは、調剤薬局の無料相談や経営診断を提供しています。
もし経営面で心配なことがあれば、お気軽にご相談ください。
『2026年度改定における在宅業務に係る要望事項 ー薬剤師の個人宅向け在宅業務実態に関する大規模調査よりー』と
『2022年度 訪問介護の経営状況について』
『訪問介護、5分550円で「保険外」の困りごとお手伝い SOMPOケア』
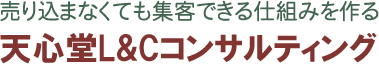
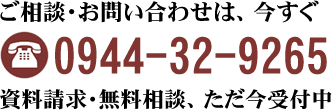
コメントを残す