薬局経営に不可欠な利益に直結する「最重要要素」とは
こんにちは。
元調剤薬局経営者で中小企業診断士・キャッシュフローコーチの梅崎実です。
最近は調剤薬局や中小企業の資金繰りや経営改善のご支援を中心に活動しています。
このブログでは調剤薬局経営に役立つ情報を発信しています。
今回は「加算算定が薬局経営に与える影響は、きっとあなたが思っている以上に大きい」というお話をします。
2025年も半分が過ぎました。
そろそろ、次回の改訂に向けた情報が飛び交い始める時期ですね。
調剤報酬改定の情報はたくさんの方が発信しているので、そちらにお任せします。
このブログでは
「もし今まで取れていた加算が取れなくなったら、経営にどれくらい影響があるか」
「取れないと思っていた加算が取れるようになったら、どれくらい経営が安定するか」
などを考えてみたいと思います。
薬局経営における売上と利益
加算の話をする前に、まずは薬局のお金の流れを軽く振り返っておきましょう。
薬局の収入=売上は、大きく分けて2つの種類があります。
お薬代と技術料です。
この二つを足したものが薬局の売上になります。
OTCなどもありますが、一般的な薬局では比率的に大きくないので、今回は無いものとします。
具体的な数字がないと分かりにくいと思うので、「第15次業種別審査辞典」という、金融機関や企業が融資や取引先の審査を行う際に活用する資料を参考に、調剤薬局のモデル損益計算書を作ってお話ししますね。
※薬代と技術料の内訳は資料に記載がないので、ざっくりしたイメージです。
さて、売上から売上原価を引いたものを粗利といいます。
売上原価は薬の仕入れ代金だと思ってください。
先ほどの図では変動費と記載していますが、売上原価と読み替えてください。
※大手チェーンなど、売上原価に薬剤師の給料などを入れている企業もありますが、話が分かりにくくなるので、ここでは売上原価=薬の仕入れ代金とします。
※業種別審査辞典も製造原価が計上されていますが、話が難しくなるので、製造原価に計上されている経費は売上原価や人件費、その他の経費等に計上しなおしています。
例えば売上が10,000千円、薬の仕入れ代が6,284千円の場合、粗利は差し引き3,716千円となります。
【売上10,000千円-売上原価6,284千円=粗利3,716千円】
そこから人件費や家賃、光熱費など、毎月かかる費用=固定費を引いた残りが利益です。
固定費の多くを占めるのが人件費です。
人件費が2,472千円、その他の経費1,121千円とすると、残る利益は123になります。
【粗利3,716千円-人件費2,472千円-その他の経費1,121千円=123千円】
図に記載されている固定費は、人件費とその他の経費を足したものだと思ってください。
【人件費2,472千円+その他の経費1,121千円=3,593千円】
10,000千円の売上があるのに、残る利益は123千円。
しかもこの利益から利息や税金の支払い、借入金の返済、設備の更新を実施したり、万が一の備えを蓄えないといけないわけですから、いかに会社にお金を残すのが大変か分かりますね。
薬局経営において、粗利が重要な理由
私はセミナーなどで企業のお金の流れをご説明するときは、「粗利が大事です!」と繰り返しお伝えします。
なぜなら、粗利が本当の意味での企業の収入だからです。
家計で言うところの手取りが粗利です。
額面30万円の給料をもらっていても、実際に口座に振り込まれるのは24万円くらいですよね。
その範囲内で食費や家賃、教育費などの生活費を払い、娯楽を楽しみ、貯金をするわけです。
手取り以上の暮らしをすると、すぐ借金生活になってしまいます。
それと同じように、企業も粗利の中から様々な経費を支払っていきます。
粗利の範囲で経費を賄うことができれば経営は安定しますが、粗利以上に経費が掛かってしまうと赤字になります。
赤字の状態が長く続けば、会社からお金がどんどん流出してしまいます。
放置すれば資金が尽きてしまい、薬局経営は続けられなくなります。
そうならないように、事業が続けられるだけの利益を上げていかなければなりません。
事業が続けられるだけの利益のことを、私は「生存利益」と呼んでいます。
私の勝手な造語ですが、生きるために必要な糧を稼がなくちゃいけないのは、人も会社も同じです。
さて、その粗利に大きな影響を与えているのが「加算」です。
加算が薬局の粗利に与える影響
先ほどもお話しした通り、調剤薬局の売上は、薬代=薬価と技術料で成り立っています。
売上と売上原価の差が粗利です。
粗利の内訳をみてみると、薬価差益と技術料に分かれます。
薬の仕入れ代と薬価の差額が「薬価差益」ですね。
例えば薬を90円で仕入れたとします。
その薬の薬価が100円だった場合、10円の利益が生まれます。
これが薬価差益です。
ただ、薬価差益は薬価改定ごとに小さくなりますし、医薬品卸は薄利で苦しんでいるので、今後多額の薬価差益を得るのは困難になるでしょう。
もう一つの売上の源なのが技術料。
調剤基本料のように、処方箋受付ごとに算定するものもあれば、薬剤調整料のように調剤内容によって算定するかしないか変わるものもあります。
また、地域支援体制加算や後発医薬品調剤体制加算などのように、薬局の運営体制や調剤体制を評価する加算もあります。
他にも様々な点数がありますが、話がややこしくなるので技術料の種類についてはここまでとしましょう。
さて、様々な技術料がある中で、薬局経営に大きな影響があるのは加算の算定だと思います。
調剤基本料は基本的に算定できる条件が決まっていますし、薬剤調整料も処方内容によって算定できる内容がほぼ決まります。
一方、加算は国の方向性に従って付加価値の高いサービスを提供することで算定できるようになります。
もちろん、算定には様々な課題やハードルがあり、それらをクリアしなくてはなりませんが、自助努力で収益をアップさせ、経営を安定させることができるのです。
仮に先ほどのモデル決算書を示した薬局が年間1,000枚の処方箋を応需していたとしましょう。
だいぶ少ないですが、分かりやすくするために、仮に年間1,000枚とします。
地域支援体制加算1を算定できるようになれば、処方箋1枚につき320円売上が増えます。
320円×1,000枚で、年間320千円の売り上げが増えます。
加算が増えても薬の仕入れが増えるわけではないので、これはそのまま粗利の増加になります。
もし人件費やその他の固定費も増えない場合、利益がそのまま320千円増えるのです。
算定前の利益は123千円ですが、算定後は443千円。
利益が3.6倍になるわけです。
そうなれば、税金や利息の支払い、借入金の返済、設備投資の支払いなども楽になりますよね。
※もちろん、処方箋枚数や加算の内容によってどれくらい利益が増えるかは変わります。
あくまでも上記の前提で計算してみたら3.6倍になった、ということです。
薬局経営を数値で把握できることが大事
加算算定は薬局経営への影響がこれほど大きいのですから、積極的に算定すべきだと思います。
もちろん加算算定には様々な考え方があって良いと思います。
経営者の価値観に基づいて、「加算を算定しない」というのであれば、それも一つの選択肢です。
ですが、給与の支払いが遅れたり、社会保険料が納められなくなったり、薬の仕入れ代が払えないような状態になってしまっては元も子とありません。
薬局は地域にとって薬の流通と健康づくりを担う重要なインフラですから、持続的な経営をすることが使命です。
経営が苦しくなっていたり、資金繰りが厳しくなっているなら、算定できていない加算を算定するように動かなくてはなりません。
にもかかわらず、加算算定に取り組まない薬局さんも多いのです。
薬局だけでなく、経営難に陥っている介護事業所にも同じ傾向があります。
なぜ、経営が苦しいのに加算算定に取り組まないのか。
人の問題や要件の問題で算定のハードルが高いという場合もあるでしょう。
しかし私の見てきたケースでは、そもそも加算算定によって利益がどれくらい増えるのか、試算したことすらない薬局経営者が少なくありません。
それどころか、現状の経営を続けているとこの先どうなるのか、いつまで資金が持つのかなど、経営にまつわる数字自体を理解できていないことが多いのです。
数字を把握できていないから、まずい経営を続けてしまう。
苦しくなっているのに、具体的な手を打たないままにしてしまう。
まるで、健康診断を受けなかったり、血液検査の結果もみようとせず、生活習慣病が進行してしまう方とそっくりです。
例えば血糖値が高い状態を放置するとどうなるでしょうか?
糖尿病になりますね?
それでも放置すれば?
動脈硬化が進み、重大な病気につながります。
失明や足の切断などのリスクも高まりますよね。
そうならないよう、血糖値を測定し、しっかり対策してほしいと思いますよね?
経営も同じです。
経営の結果は数字となって数字に表れます。
経営の問題を発見するには、数字を見るのが一番早くて確実なのです。
まずは自社の経営の現状を数字で把握しましょう。
利益はきちんと出ているでしょうか?
売上や利益の数年間の推移はどうなっていますか?
借入金がどれくらいあり、毎月どれくらい返済しているか把握していますか?
新たに始まる返済があったり、分包機の買い替え予定などが迫ってきていませんか?
将来的な出費に備えて、現金は十分ありますか?
今の経営を続けていれば、この先どうなるかを数字でシミュレーションしてみましょう。
万が一困難な状況になることが予測されるなら、余力があるうちに対策を講じましょう。
もし、あなたが数字を見るのが苦手だったり、自信がない場合はご相談ください。
一緒に現状を分析し、対策を検討しましょう。
きっと、一人では見えない課題が見えてきたり、やるべきことが整理できると思います。
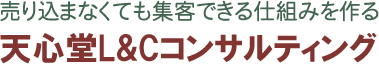
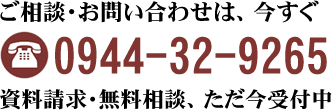
-300x265.png)
-300x266.png)
-300x266.png)
-1-300x179.png)
コメントを残す